入社後に聞いてた話と違うと感じたら?諦めずに行動を起こすための3つの選択肢
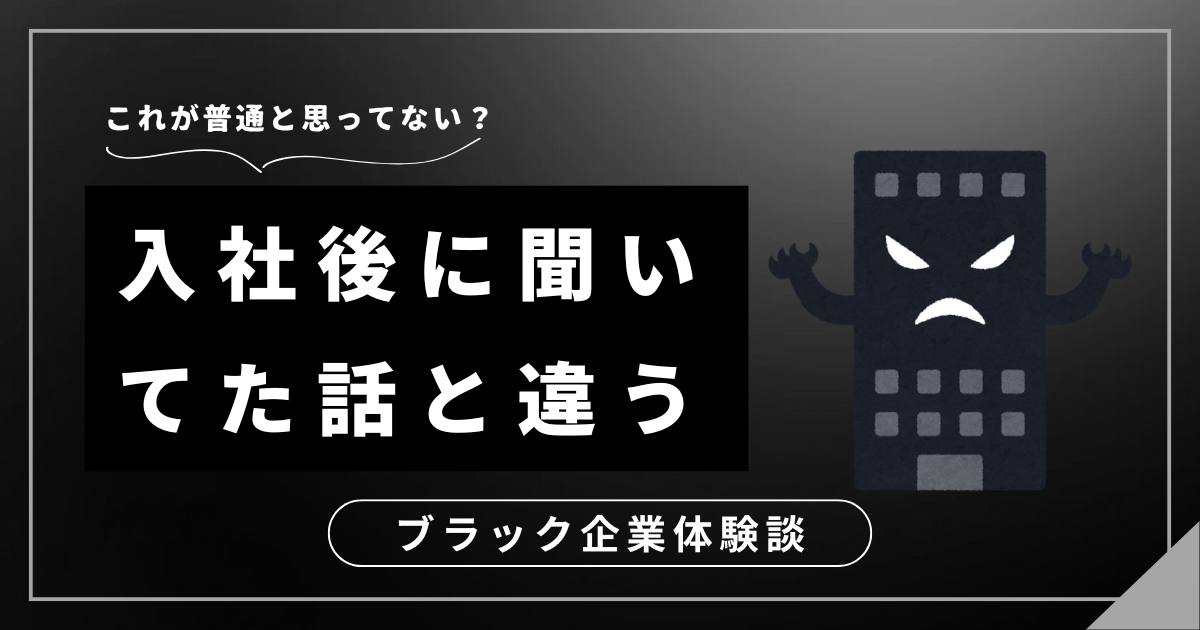
入社後に聞いてた話と違うと感じているあなたへ。
「こんなはずじゃなかった…」
そんな思いを抱えながら、毎日会社に通っていませんか?
面接時には
- 「残業はほとんどありません」
- 「休日出勤の予定はありません」
と説明されたのに、実際には残業が当たり前で、休日出勤も増えていく一方。
期待を胸に入社したはずなのに、現実は違っていた…。
そんな状況に戸惑い、悩み、もしかしたら自分に何か問題があるのではないかと、自分を責めてしまうことさえあるかもしれません。
でも、それは決してあなたの責任ではありません。
この記事では、入社後に「聞いていた話と違う」と感じて悩んでいるあなたに向けて、具体的な対処法や解決策をご紹介します。
より良い環境で働くための一歩を、一緒に考えていきましょう。
【体験談】入社後に聞いてた話と違う状況に絶望…でも転職して人生が変わった話
WEBアンケートで募集したブラック企業の体験談を紹介します。
私が製造業の工場に就職した時の話です。
面接では
「残業はほぼありません。週休2日制で、ワークライフバランスを重視している会社です」
と説明を受け、手取り14万円という給料も、その労働条件なら納得できる金額だと考えて入社を決めました。
しかし、入社してすぐに違和感を感じ始めました。
最初の2週間は確かに定時で帰れていたのですが、時計の音が気になり始めた3週間目から、状況は一変したのです。
- 「ごめん、今日は納期が厳しくて…」
- 「みんな残業してるから、君も頑張ってくれるよね?」
先輩からそう言われる度に、胃がキリキリと痛むようになりました。
残業は日常的になり、気づけば深夜まで工場に残ることが当たり前になっていました。
「ハァ…今日も23時か…」と溜め息をつきながら帰宅する日々。
休日出勤の要請も増え、「今月は忙しいから」という言葉が常套句のように飛び交っていました。
- 「おかしいな…面接の時とまったく違うぞ…」
- 「これって騙されたってことなのかな…」
そんな思いが頭をグルグルと巡る中、私の心と体は限界に近づいていました。
休日も「明日また仕事か…」と考えるだけでゾクッとして、布団から出られない日も。
同期入社の友人は次々と辞めていき、残された私は「自分だけがダメなのかな」と自分を責め続けていました。
- 「今月は特別忙しいから」
- 「もう少しすれば落ち着くから」
先輩たちはそう言い続けましたが、半年経っても状況は改善されず、むしろ悪化の一途を辿っていました。
休日出勤が増え、深夜残業も「当たり前」という雰囲気が蔓延。
「ピー」という機械の警告音が、まるで私の心の悲鳴のように聞こえました。
入社から8ヶ月が経ったある日、久しぶりに会った大学時代の友人に
「その会社で我慢し続けて後悔しない?」
と言われ、ハッと我に返りました。
その夜、
「このまま続けても何も変わらないんじゃないか」
という不安が押し寄せ、眠れない夜を過ごしました。
結局、入社1年で退職を決意し、転職活動を始めました。
今思えば、「すぐ辞めるのは甘え」という考えが、自分を追い詰める原因になっていたと気づきます。
転職活動では、面接で労働条件をしっかりと確認し、現場で働く社員の声も積極的に聞くようにしました。
そして今、私は新しい会社で働いています。残業も少なく、約束された労働条件がきちんと守られている職場で、やりがいを持って仕事ができています。
あの時の経験は辛いものでしたが、「これは違う」と気づいて行動を起こせたことで、むしろ自分の価値観や大切にしたいものが明確になりました。
入社後に聞いてた話と違うと感じる会社の問題点
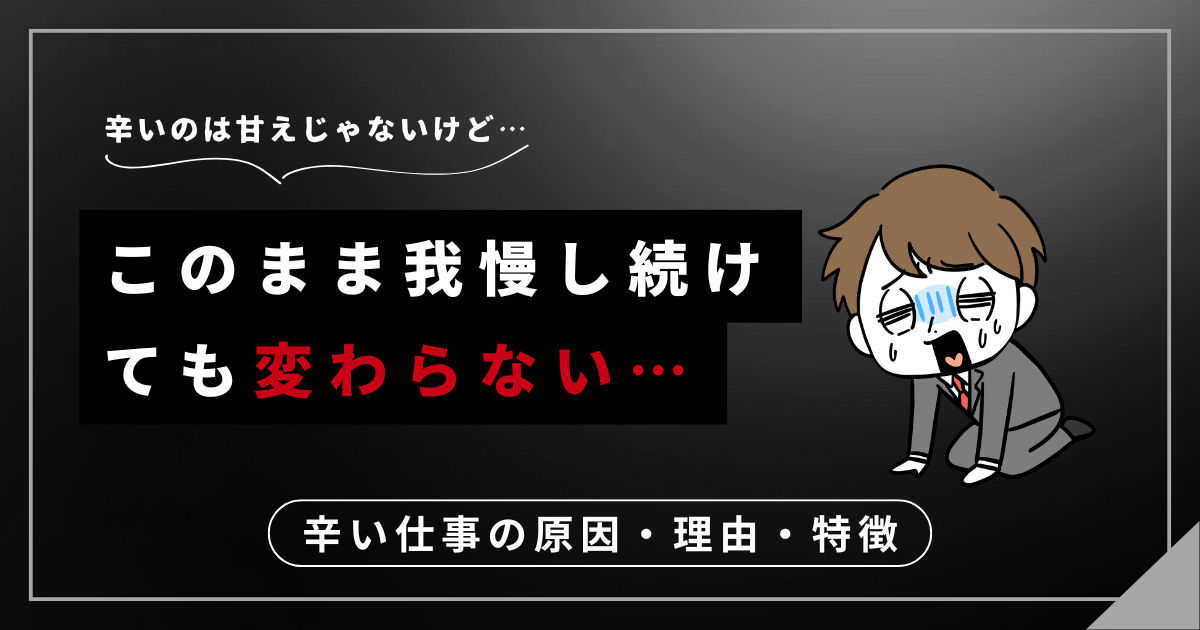
入社後に「話が違う」と感じて悩んでいる時は、本当に辛いですよね。ここでは以下の内容について説明していきますね。
- 採用時の説明と現場の実態が大きく異なる
- 会社の体制が整っていない
- 上司や先輩の意識が低い
入社後に「聞いていた話と違う」と感じる背景には、会社側の様々な問題が隠れています。これらの問題は、単なる誤解ではなく、組織としての重大な課題を示していることが少なくありません。それでは、一つずつ詳しく見ていきましょう。
採用時の説明と現場の実態が大きく異なる
採用担当者と現場の認識にズレがあります。多くの場合、採用担当者は現場の実態を把握できていないことが原因です。人事部門と現場の間でコミュニケーションが不足しており、採用時の説明が理想論になってしまうケースが多いのです。
- 「残業はほとんどありません」と言われたのに、実際は毎日残業が発生している
- 「年間休日120日以上」と説明されたが、繁忙期は休日出勤が当たり前になっている
- 「研修制度が充実」と聞いたが、実際は現場任せの見よう見まねの教育しかない
採用時の説明と現場の実態が異なることは、新入社員の信頼を大きく損なう重大な問題です。
会社の体制が整っていない
業務プロセスや人員配置が適切に設計されていません。会社の成長に組織体制が追いついておらず、場当たり的な対応に終始していることが多いのです。その結果、入社時に説明された理想的な労働環境が実現できていない状況に陥っています。
- 人手不足で一人あたりの業務量が過剰になっている
- 業務マニュアルが整備されておらず、属人的な仕事の進め方になっている
- 部署間の連携が不十分で、必要以上に時間がかかる作業が多い
このような体制の不備は、入社時の説明と現実のギャップを生む大きな要因となっています。
上司や先輩の意識が低い
職場の上司や先輩が、労働環境の改善に対して消極的な姿勢を示しています。「昔からこうだった」という意識が強く、問題のある状況を当たり前のこととして受け入れてしまっているのです。そのため、入社時に説明された理想的な環境作りへの取り組みが進みません。
- 「自分たちの時代はもっと大変だった」と改善の必要性を否定する
- 「忙しいのは仕方ない」と諦めの意識が蔓延している
- 「若手は根性が足りない」という古い価値観を持っている
上司や先輩、管理職層の意識の低さは、職場環境の改善を妨げる大きな壁となっているのです。
入社後に聞いてた話と違うと感じた時の対処法
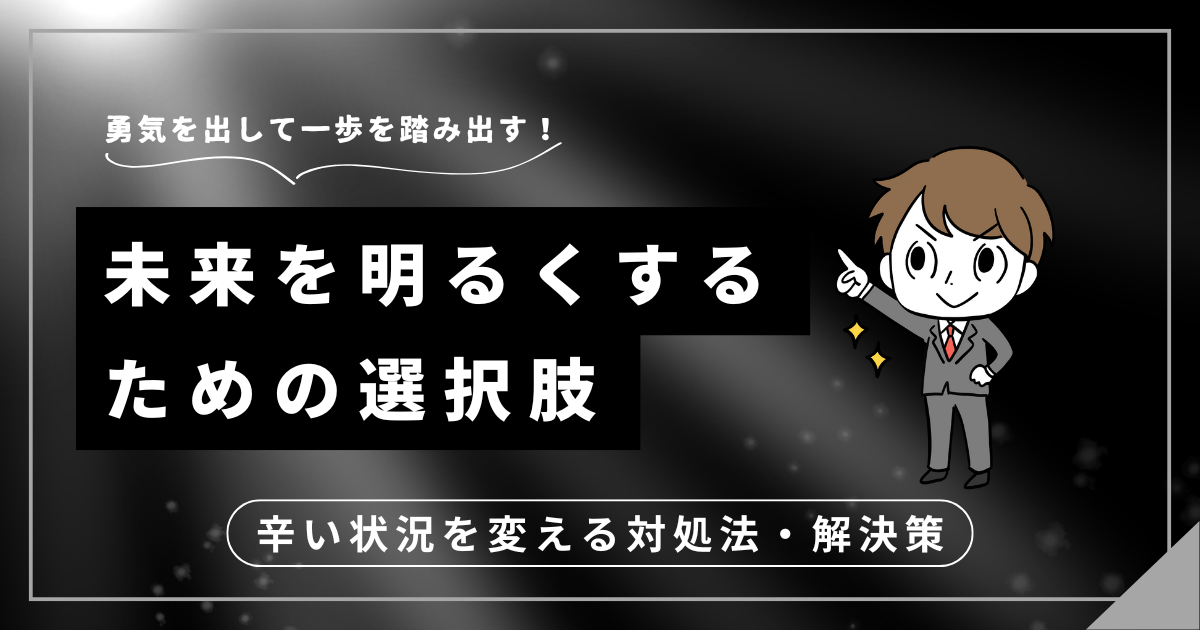
入社後に「聞いていた話と違う」と感じて悩んでいる時は、諦めずに行動を起こすことが大切です。ここでは以下の内容について説明していきますね。
- 労働基準監督署に相談して改善を求める
- 転職エージェントに登録して次のステップを考える
- 退職代行サービスを利用して円滑に退職する
状況を改善するためには、段階的なアプローチが効果的です。まずは現状の改善を試み、それが難しい場合は転職を検討し、最終手段として退職を考えることをおすすめします。それでは、一つずつ詳しく見ていきましょう。
労働基準監督署に相談して改善を求める
労働条件の相違は法的な問題になる可能性があるため、専門家に相談することが重要です。なぜなら、労働基準監督署は労働者の権利を守るための公的機関であり、会社に対して強い指導力を持っているからです。相談は無料で、匿名でも可能です。相談したことを会社に漏らすことは一切ありません。
- 残業時間や休日出勤の実態について、タイムカードや勤務記録を証拠として提示する
- 採用時の説明と現状の違いを具体的に記録し、書面で提出する
- 同僚の証言や社内メールなど、労働条件の相違を示す証拠を集める
- 労働基準監督署からの指導を受けて、会社側が改善計画を立てる
公的機関に相談することで、個人では難しい会社への改善要求が可能になります。労働基準監督署への相談は、あなたの権利を守るための重要なステップとなるでしょう。
転職エージェントに登録して次のステップを考える
現在の会社での改善が見込めない場合は、並行して転職の準備を始めることをおすすめします。特に転職エージェントの活用は、忙しい状況でも効率的に転職活動を進められる強い味方となります。なぜなら、エージェントが候補企業の選定から面接日程の調整まで、きめ細かくサポートしてくれるからです。
- 労働条件の確認を重点的に行い、同じ轍を踏まないようにアドバイスをもらえる
- 非公開求人も含めた幅広い求人情報から、希望に合った企業を紹介してもらえる
- 面接対策や条件交渉のサポートを受けられ、転職成功率が高まる
- 現在の仕事が忙しくても、空き時間に合わせた転職活動が可能
転職エージェントを活用することで、効率的かつ効果的な転職活動が可能になります。専門家のサポートを受けながら、より良い職場環境への転職を目指しましょう。
退職代行サービスを利用して円滑に退職する
状況が深刻で早急な退職が必要な場合は、退職代行サービスの利用を検討してください。特に、上司とのコミュニケーションが困難な場合や、退職を切り出しづらい状況では、専門家に依頼することで精神的な負担を軽減できます。なぜなら、退職代行サービスは法的知識を持った専門家が、あなたの代わりに退職交渉を行ってくれるからです。
- 退職の意思表示から書類の手続きまで、すべての対応を代行してもらえる
- 労働法に基づいた適切な交渉により、未払い残業代の請求なども可能
- 退職後の手続きや引継ぎについても、専門家のアドバイスを受けられる
- 精神的なストレスを感じることなく、スムーズな退職が実現できる
退職代行サービスを利用することで、心身の負担を最小限に抑えながら、確実に退職手続きを進めることができます。自分の健康を第一に考え、必要な場合は躊躇せずに専門家のサポートを受けることをおすすめします。
【Q&A】入社後に聞いてた話と違うと感じた時の疑問に回答
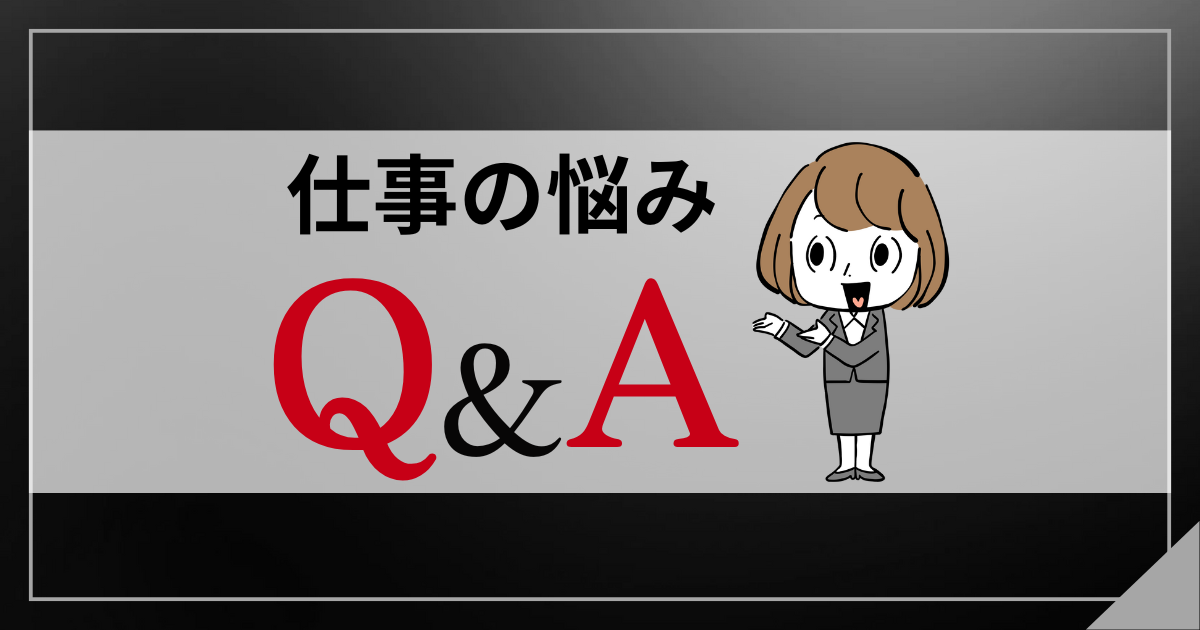
ここでは、入社後に「聞いてた話と違う」と感じて悩んでいる時の疑問について、分かりやすく回答していきますね。
- 入社後すぐに辞めるのは会社に迷惑をかけませんか?
- 面接時の説明と違う場合、法的に問題になりますか?
- 上司に労働条件の改善を求めても無視されたらどうすればいいですか?
- 入社前の説明と違う場合、どこまで我慢するべきですか?
- 話が違うと感じた時、すぐに転職活動を始めても大丈夫ですか?
それでは、一つずつ詳しく見ていきましょう。
入社後すぐに辞めるのは会社に迷惑をかけませんか?
会社に迷惑をかけることを心配する気持ちは理解できますが、自分の健康や将来を優先することは決して間違いではありません。採用時の説明と実態が大きく異なる場合、それは会社側の責任でもあります。
経歴的なデメリットを気にする方もいますが、早期に状況を改善することで長期的にはプラスになることが多いでしょう。
面接時の説明と違う場合、法的に問題になりますか?
採用時に説明された労働条件と実態が著しく異なる場合、労働契約法における信義則違反や、場合によっては詐欺的行為として法的な問題となる可能性があります。
特に、残業時間や休日出勤の頻度、給与条件などが大きく異なる場合は、労働基準監督署に相談することで改善を求めることができます。
上司に労働条件の改善を求めても無視されたらどうすればいいですか?
上司に改善を求めても変化がない場合は、人事部門や本社に相談することを検討しましょう。労働組合がある場合は組合に相談することも効果的です。
社内での解決が難しい場合は、労働基準監督署や労働局の総合労働相談コーナーに相談することで、専門家のアドバイスを受けることができます。
入社前の説明と違う場合、どこまで我慢するべきですか?
我慢は解決にはなりません。むしろ、長期間の我慢は心身の健康を損なう可能性があります。理不尽な状況に耐えることは美徳ではありません。
できるだけ早い段階で具体的な改善策を考え、行動を起こすことが重要です。状況が改善される見込みがないと判断したら、転職を視野に入れることをおすすめします。
話が違うと感じた時、すぐに転職活動を始めても大丈夫ですか?
問題ありません。むしろ、早めに転職活動を始めることで、より良い選択肢を冷静に検討できます。
転職活動は情報収集の段階から始められます。実際の転職時期は慎重に検討しつつ、並行して転職市場の動向やスキルアップに必要な情報を集めることは、むしろ賢明な選択といえるでしょう。
【まとめ】入社後に聞いてた話と違うと感じて悩んでいるあなたへ
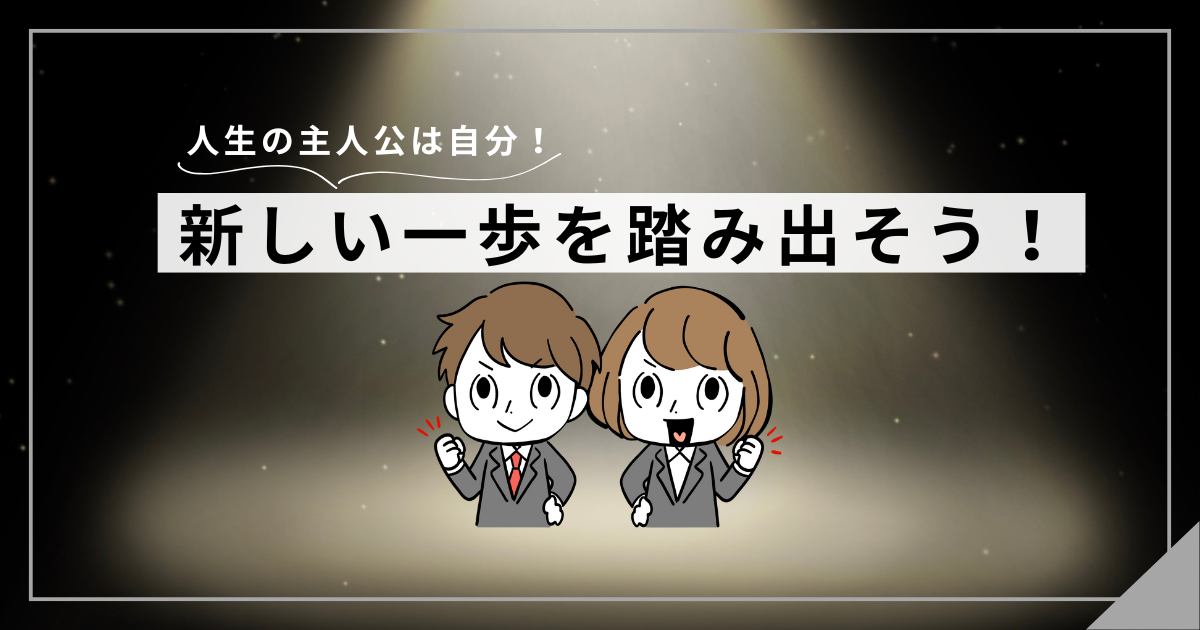
入社後に「聞いてた話と違う」と感じて悩んでいるのは、あなただけではありません。
このような状況に直面することは、誰にでもあり得ることです。
大切なのは、この経験を無駄にせず、より良い選択につなげていくことです。
今の状況を「我慢するしかない」と諦めないでください。
まずは現状の改善を試み、それが難しい場合は転職という選択肢も視野に入れましょう。
あなたの人生において、働きがいのある環境で過ごすことは当然の権利です。
今回の経験は、きっと次のステップで活きてきます。
より良い環境で働くための「気づき」として、この経験を前向きに捉えていきましょう。
あなたの勇気ある決断が、必ずより良い未来につながっていくはずです。
「本当は今すぐ会社を辞めたいけど、辞める前に次の転職先を探しておきたい」という場合は、できるだけ早く転職活動を始めることをおすすめします。
もし、あなたがブラック企業で働いていて、「上司が怖いから会社を辞めたいと言えない…」と悩んでいるなら、退職代行サービスにサポートしてもらうのも一つの手です。



